Adoã®ããã£ããããã瀟äŒçŸè±¡ãšåŒã¹ãªãçç±ãšã¯…ïŒ
Adoãšå°ŸåŽè±ã®éã
ããŠããããã¹ããœã³ã°ãšããã°ãã¯ã "å°ŸåŽè±" ã ããã é«æ ¡åšåŠäžã«ããã¥ãŒããç¹ã«10代ã®é ã¯ã瀟äŒãžã®åæã»çåããåæ¯é ããªã©ãè¡šçŸãããæ ¡å æŽåãåŠçã«ãã飲é ã»å«ç ã暪è¡ããåå·®å€æè²ãåéšæŠäºã®ã²ãã¿ãé²åããŠããæåã®ç¬ç¹ãªæ代äžçžãšçžãŸã£ãŠç€ŸäŒçŸè±¡ãšãªã£ãããã¹ã¡ãã£ã¢ã¯åœŒãã10代ã®æç¥ããšåŒã³ãè¥è ã®ä»£åŒè ãšããŠæ代ããæ±ããããŠããã ãããŠãµãšæã£ãã 什åã®ãããã¹ããœã³ã°ããã£ããããã«å¯Ÿããæ代ã®åå¿ãšãæåã®å°ŸåŽãèãããã®æã®æ代ã®åå¿ãæããã«éãã®ã§ã¯ãªããã äžèšã§èšããšãèãæãå·»ã蟌ãã "瀟äŒçŸè±¡ã«ãªã£ãŠããåŠã" ã®éãã§ããã å°ŸåŽãèããŠãè¥è ã¯çãã ãã€ã¯ã§èµ°ãåºããæ ¡èã®çªã¬ã©ã¹ãå©ãå²ã£ããããããããã£ãããããèãã什åã®è¥è ã¯æãããŠäœãããã®ã...ãæ²ã«åŸãã°ããã¯ã âããããâ ãšé£åŒããã®ã§ãããæ ¹æ ã¯å¥åº·ãšå€©æãããããããæ¹è¶ãã©ãããŒãã¯æ¹è¶é£²æã ããããšã匷åŒãªåæšäºå ¥ã§å¥åº·ãã¢ããŒã«ãããããçæã«æ®ã£ã30æã®åçããå³éžãã1æãSNSã«èŒããŠãã¢ãã£ãªãšã€ãã»ã€ã³ã¹ã¿ã°ã©ããŒããåä¹ã£ãŠå€©æãèªç§°ããã ç³ãé ããããæ¬èšäºãæžããŠããç§ã¯çŸåšå€§åŠ2幎çã®åŠçã§ãé 調ã«ããã°ãã®æ¥ã§3幎ã«ãªãã é 調ã«ããã°ã就掻ãå§ãŸãåºãã瀟äŒãšã®æ¥ç¹ãåŸã ã«å¢ããã®ã倧åŠ3幎çãšãããã®ã ã瀟äŒãžã®ã¹ããããšããŠ1æ©2æ©ãšå€§äººãžã®æ©ã¿ãå®æããããšããã®ããã®å€æãªææã®1ã2幎ã«ãããå€åã ãããäžå¿ã什åã®è¥è ãšããç«å Žã§ççŽãªææ³ãè¿°ã¹ããšããããŸã§å人ã®æèŠã ããããã£ãããããšã¯æ代æ¹å€ãšããããææ¥æã®éå°åå¿ã«è¿ãæ§ãªå°è±¡ãæã£ãã å°ŸåŽãããããã瀟äŒçŸè±¡ãèæèŠã§ã¯ç¥ãåŸãªãçºããã®2è ã®å¯Ÿæ¯ã« âæåãšä»€åâ ã®æ代æ¯èŒãèœãšã蟌ãããšã¯é£ããã ããããå®æãšããŠãAdoã«å¯ŸããŠåããããè¥è ã®èŠç·ã¯ãäžæºã代åŒããŠãããå°ŸåŽã象城çååšãšããŠåŽããè¥è ã®èŠç·ã®æ§ãªç±ã垯ã³ãŠãããšã¯æããªãããAdoããããæãã§ããæ§ã«ãæããªãã ãããã®éãã¯ãªãçãŸããŠããã®ã...ã以äžã§ã¯ãã®åãã«ã€ããŠèããŠãããããå°ŸåŽè±ã®èŠãã¿ã®çç±
ãªãå°ŸåŽã®ãããã¹ããœã³ã°ã¯ãè¥è ãç œåãã瀟äŒçŸè±¡ã«ãªããAdoã®ãœã¬ã¯ãªããªãã®ã...ã ç§ãæãã«ãããã¯ãã«ãŒã«ãåãå·»ã人ç©çžé¢ãå€åããçºããšèããŠããã ã«ãŒã«ãšããã®ã¯ãäœã人ãšããã«åŸã人ã®äºé 察ç«ã®æ§å³ã«ãªããã¡ã ããéèŠãªç¬¬äžã®ãã¹ãããããšç§ã¯æã£ãŠãããããã¯ãã«ãŒã«ã説æãã人ãã§ãããããªãé»é«ªãããªãããããªãã®ãããšåãçåŸãšããããããæ ¡åãã«ãŒã«ã ããã ããšããå çã®è°è«ãæ©æŠã垯ã³ãªããå¹³è¡ç·ã®ãŸãŸã«ãªãã®ã¯ããã®ç¬¬äžã®ãã¹ããèŠããŠããªãããã§ã¯ãªãã ããã...ã ããããªæ ¡åã«ã¯æå³ããªããæ¹å€ãã¹ãã ãããšãã蚎ããäžåã«æ±²ã¿åãããªãçç±ã¯ããã®å çãã«ãŒã«ã âäœã人â ã§ãªãã«ãŒã«ã â説æãã人â ã ããã ãšèãããããæã®å çãæè²å§å¡äŒãªã©ã®çµç¹äžéšãã²ããŠã¯æåãæ £ç¿ãªã©ã®ææ§ãªåæ圢æã«ãã£ãŠåºæ¥äžãã£ãã«ãŒã«ã¯ãè€éãããŠç®ã®åã®å çã«ã¯100ïŒ çŽåŸã®ãã説æãåºæ¥ãªãã ãã®æ§é ãèŠããªããŸãŸçäžå°œãšãæããå¶éãç¶ãã°ãå¿ ç¶çã«å€§äººç€ŸäŒãžã®äžæºãšããã¬ã¹ãæºãŸããããã«åæ¯é ãæããœãŠã«ã·ã³ã¬ãŒã»å°ŸåŽãç«ãã€ããã°ã倧ççºã«ãªãã®ã¯æ³åã«é£ããªãã äžæ¹ã§ãä»ã®è¥è ã¯äžæºãæºãŸããšã©ãããã ããã...ã çãã¯ãã€ã³ã¿ãŒããããã§ããã 誰ãã«ãŒã«ã®æ§é ãéã説æããã£ãŠãããªãã£ãæãšã¯éãããããã«ã¯èšå€§ãªéã®æ å ±ããããããã¹ããåç»ãªã©ãã®åªäœãæ§ã ã§ãèªåã«ãã£ãæé©ãªæ段ã§æ å ±ã«ã¢ã¯ã»ã¹ã§ãããããã§ã¯ããããã人ãããããäºè±¡ã説æããŠãããç°å¢ãæŽã£ãŠãããSNSãªã©ã§å€§ããå ±æãçãã 話é¡ããçŸå Žã§ã®çŸç¶èŠçŽãã®ãã£ããã«ãªãäŸãå€ãã ããããé©åºŠãªã¬ã¹æãã«ãªã£ãŠããã®ã§ããããã¹ããœã³ã°ãçç«å€ãšããŠã®æ©èœã倱ããããåŸãªãããšããã®ãç§ã®çµè«ã ã å¿è«ãèŠãã ãã§ãªãçºä¿¡è ã«ãªãæããªã£ãäºããããããSNSã®éèŠãªåŽé¢ã§ããããããã人ãã¯ãªãšã€ã¿ãŒã«ãªããã®ã§ã³ã³ãã³ãã®çµ¶å¯Ÿæ°ã¯æãšã¯æ¯ã«ãªããªãã以åã«ã¯ç¡ãã£ãæ§ã ãªã³ã³ãã³ãæåãçºéããŠãããšããæå³ã§ã¯ãä»ã®æ代ãªãã§ã¯ã®åŒ·çãªã¡ãã»ãŒãžãæãã·ã³ã¬ãŒã¯ãã®ä»€åã«ãå€ãååšããŠããã æãã®ã ããå°ŸåŽã®èŠãã¿ã¯ä»£åŒè ã«åŸ¹ããæ ã®ãã®ã§ããããããããªãã誰ãã®æ°æã¡ãæãããšãæ±ãããããããå éšåããŠèªåã®æããšããæ¿ãã£ããªãã°ãèªåãèŠããªããªãã®ã¯åœç¶ã§ããããããªã£ããªãããã誰ãã«å©ããŠããããããªããããããé³æ¥œã®åºçªã ã äžäŸã ãããšã«ã·ã«ã®ãææ³ç¯ããšãã楜æ²ãããã "ä»äººã«åªãããããã«ãã®å¿ãããããã®ã"ããšãã蚎æ±åã®åŒ·ãèšèããå§ãŸãã"æ»ã«ãããªããçããããªã ã ããè©©ãæžããŠã" ãšããã¢ãŒãã£ã¹ããªãã§ã¯ã®èŠæ©ãªã¯ãªãšã€ãã£ããã£ãæããããMusic Videoã¯ã¢ãã¡ãŒã·ã§ã³ã®ã¹ããŒãªãŒä»ç«ãŠã«ãªã£ãŠããã匷çããã人ãçŽ é¡ãé ãããã«æ¥åžžçã«ä»®é¢ãä»ããŠããã·ãŒã³ãæãããŠããã ãããŠãæåŸã®ãµãã«å ¥ã3å10ç§èŸºãã§ç²ãåã£ã匷çã¯ä»®é¢ãå€ãã®ã ããé¡ãèŠãŠé©æãããä»®é¢ã®äžã«ãããäžæä»®é¢ããã£ãã®ã ããã®äžã«ããããã«ãã®äžã«ãæ§ã ãªä»®é¢ã匵ãä»ããŠãããå¥ããã©å¥ããã©çŽ é¡ãèŠããŠããªãããã®ãµãã§ã®æè©ãããã ... åã®èšèãåã¿ãã å ¥ãç©ããªãäž¡æã§åã㊠ãã€ããåã最ã ãã®æãåŸ ã¡ãªãã ä»ããããä»®é¢ã«ãçŽ é¡ãä¹ã£åããããšããé å©ãšç §ããåãããŠããããŸã§ç§ãå人çã«å°ãããææ³ç¯ããšãã楜æ²ã®è§£éãå°ŸåŽã«ã¶ã€ããããä»äººã®èšèã飲ã¿ç¶ããäºã§ããæžããçããªããªã£ãŠãããªãããããŠããããèªèŠã§ããŠããªãã£ãã®ãªããéããŠããã ããããããããšèããŠããŸã...ã âå°ŸåŽããšã«ã·ã«ãèããŠãããªããæŽå²ã¯å€ãã£ãŠãããããããªããâ ããæã£ãŠããæŽå²ã«ã¿ã©ã¬ãã¯ãªããã ãããæã ã«ã§ããããšã¯äžã€ãããªããä»ãçããããã®ç¬éãšäººã«åãåããåœã®æå³ãããããªã人ã¯ãã«ã³ã¶ãã€ãªãªã®ãåœã«å«ãããŠããããèããŠãããçããã®ãèŸã人ã¯ã森山çŽå€ªæã®ãçããŠãããšãèŸããªãããèããŠããã倩åœã®å°ŸåŽãããã¿ããã®ãçããŠãããã ããªããèããŠããããŸã ãŸã ããããŸã ãŸã ãããã§ããèããŠã»ããæ²ã...ã ãšããããšã§æ¬¡å以éã¯...ããããªãã€ã¯ãããèãã...çãªã®ãšããããšã«ã·ã«ã®æ¥œæ²ãç¬æãšåèŠã§é¬Œæ·±æãããããã¿ãããèŽããããŠåœŒå¥³ã«ãã©ãã話ïŒå®è©±ïŒã...ã¿ãããªèšäºãæžãããšèããŠããŸãã æåŸãŸã§èªãã§ããã ããæé£ãããããŸãã -- ã¡ãã£ã¢éå¶ïŒEvening Music Records Inc.ã2022幎泚ç®ãimaseãasmiãªã©… TikTokã§æ³šç®ã®ä»æ¥ãŠãã¢ãŒãã£ã¹ã3éžã
imase - 代衚æ²ãHave a nice dayã
ãŸãã¯ããã¯ãimaseã é³æ¥œæŽ»åãå§ããŠããããã1幎ãšãã21æ³ã 代衚æ²ã®ãHave a nice dayãã¯TikTokç·åçåæ°ã3ååãè¶ ããã»ã©ã®ããããšãªããç¶ããéé¿è¡ãã§ãæ°åã䌞ã°ãããµã³ãã©ãŒãçšããé»åçãªé³ãšããŽãã£ãŽãã£ããããªãé³æ°ã®ãã©ã³ã¹ãå¿å°ãããéšãããããã§éšããããªãã å人çã«åœŒã®ãªã©ãã¯ã¹æãç¹åŸŽçã ãšæã£ãŠãã æ声ãè¡šæ ã«ããæå³ã§ç¡æ©è³ªãªå°è±¡ããããåãŸãèœã¡çããŠããŠãæ·¡ã ãšããŠãããã ãææ ã®è¡šçŸã¯ã¡ãããšããæãã ã©ãã®ã¹ã¯ãŒã«ã«ãŒã¹ãã«ãå±ããªãã女å人æ°ã§ãã¹ã3ã«å¿ ãé£ã蟌ããã¡ãããã¹ããªã¢ã¹å³ãæããããæåŠç·åã®ãããªæãã äŒã¿æéã¯å€§äœå¯ãŠããèªæžããŠãã æ°ããåŠå¹Žã§äžç·ã®ã¯ã©ã¹ã«ãªã£ãŠããšãªããšãªãå¬ãããªããã©ãäžåãäŒè©±ããªããŸãŸåŠå¹Žçµããæãã ç¥ããªãéã«åŠå¹Žã®ããã³ããšä»ãåã£ãŠããããã TikTokèŠãŠãŠããHave a nice dayãã®ãã£ãããŒãªãµãã®æå±åç»ãåã£ãŠããæã¯2ç§ã§ããããæŒããã ã·ã³ãã«ãªã³ãŒãä¿¡ä»°ã®ç¹°ãè¿ãã ãã©ãæ²ãšããŠã®å±éã¯æ©ããéå§ããããã¿ãª30ç§ã§ãµãã«å ¥ãïŒçã£ãŠãã®ããïŒã ãµã³ãã©ãŒïŒããœã³ã³ã®æšªã§ãã³ãã³å©ããŠãããïŒã§åŒŸãèªãã£ãŠã®ãå·®å¥åã«ãªã£ãŠãã®ããç¥ããªãã@imase119 ãHave a nice dayãã³ããçŠã§æããããšãæããŸããïŒã#ããªãŒããŒZ #匟ãèªã #ãªãªãžãã«æ² #ã«ããŒããŠã ⬠Have a nice day 匟ãèªãver. - imase
asmi - 代衚æ²ããšã¯ãããã
倧éªåºèº«ã®20æ³ãMAISONdesãšãããŠãããã§çºè¡šããããšã¯ããããã¯2021幎ã«SNSã§æã䜿çšããã楜æ²ãšãªããä»ã®ã¢ãŒãã£ã¹ããšã®ã³ã©ããªã©ã§ã話é¡ã«ãªã£ãŠããã å人ãasmiã®ããšãããã³ã¯ã䌌åã声ãããŠãããšè¡šçŸããŠããã èšãããšããŠãããšã¯ãªããšãªããããæ°ãããã 䞻匵ã匷ããããªããçœã£ãœããã³ã¯ã å®å€ç°ãã«ã«ãšaikoã足ããŠïŒã§å²ã£ããããªãçœã£ãœããã³ã¯ã ã¯ã©ã¹ã®ç·åå šå¡ãšä»²è¯ããªãã¿ã€ãã äžåºŠã¯å¥œãã«ãªããã©ããããããã€ãšã仲è¯ããã ãã£ãŠæã£ãŠèã¢ãªãããªãããšãèªèŠããã è¥ã女æ§ã¢ãŒãã£ã¹ãã¯å€ã«æ°åããã«æ°æã¡ããæã£ãŠããšãããã ãã§ã³ã³ãã³ããšããŠæç«ããã£ãŠã®ãäœçŸããŠãããã«æããã é»ååè·¯ã®ãã¹ãå匷ããŠãæã«ã ãºãããŠãæ¯æãã«ã森äžèããã£ãããã£ãŠããã·ã§ãã¯ãªããšãã£ãŠããè¬ã®å€§åå©ãåéãããåºããããšããã£ãŠããé¡ã®åã§ç¬é¡ã®ç·Žç¿ïŒæéãã£ãŠããåçãïŒæ¬ã«ãªã£ãã ã¿ããªç²ããŠããã ãšæãã ãã®äž»èªã森äžèããasmiã«å€ãã£ãŠãåãåçã§æ»ãããã asmiãããããªãã¯åãç¹ããªããçŽç²ãªç¬é¡ã§æã£ãŠãã ããã@the_first_take #THEFIRSTTAKE #MAISONdes #ãšã¯ããã feat. #åã¬ã,#asmi #äžçºæ®ã ⬠Yowanehaki - MAISONdes
ãããªã - 代衚æ²ãã³ã€ã³ã©ã³ããªãŒã
TikTokãã€ãã£ãã®ãªã¹ããŒã«ã¯ãŸã èªç¥ãæµ ããããããªãããæ¯åã®è·¯äžã©ã€ãã§100人以äžãéããé客åãçºæ®ããŠããããããªããã ãã³ã€ã³ã©ã³ããªãŒããšããã¿ã€ãã«ãš â1æ¥1æ¥ã倧äºã«ããâ ãšããã¡ãã»ãŒãžæ§ãã話é¡ãåŒã³ãç§ã®ã¿ã€ã ã©ã€ã³ã«ãæµãçããã æµæ¯å¯¿ã®LIQUIDROOã§è¡ãããã¯ã³ãã³ã©ã€ãã§ãã®æ矀ã®æå±åãäœæããŠããã®ã ããSNSã§ã®å€§ããªããºãã«äœåãæ®ããªãããããŸã§äººãéãããã®é åã¯ç¢ºããªãã®ã ã£ãã ããšMCã®ããŒã¯ãæ®éã«é¢çœãã£ãã ãäžèŸæãã§çµ¶å¯Ÿãã人ã ãšæãã ã©ã€ãã§èŠããèšèã®éãããã¡ãã»ãŒãžã®çã£çŽããããèŠãã人éæ§ããTikTokãªã©ã§ã®ãã¡ã³ããã®åå¿çã®é«ãã«ç¹ãã£ãŠãããšã¯ééããªãã-- ã¡ãã£ã¢éå¶ïŒEvening Music Records Inc.@pinku_kinoko æ²ããããšããå¬ããããšã«æ¶ãæµããããªã#ãããªã#ã³ã€ã³ã©ã³ããªãŒã@kyanai_music#è·¯äžã©ã€ã #ãªãªãžãã«æ² #赀髪ããã·ã¥ ⬠ãªãªãžãã«æ¥œæ² - natyyyy
ã¢ãžã«ã³ã®æè©ã¯ãäžçã®å šå¡ã幞ãã«ã§ãããããããªã
ã¢ãžã«ã³ã®ãã£ããããšã¯
ãããŠããã©ã³ã¡ãæèã®é«ã人ç©ã®äŸãšããŠæããŠãã人ç©ãã¢ãžã¢ã³ã«ã³ããŒãžã§ãã¬ãŒã·ã§ã³ã®ããã³ããã³... åŸè€æ£æã§ããã äžåŠçã®éåäŒã§ããœã©ãã³ãã®ãµãã«åãããŠç©ºæã®åãåŠå¹Žå šå¡ã§æ«é²ãããšãããæãäžãªåºãç©ããã£ãã®ãç§ãšã¢ãžã«ã³ã®åºäŒãã ã£ãã ãœã©ãã³ã¯ã¢ãžã«ã³ã®ä»£è¡šæ²ã®äžã€ã§ããã æµ éãã«ãã«ãããã³ããéããŠäººéæš¡æ§ãæãã挫ç»ããœã©ãã³ãã®æ ç»åã§åã¿ã€ãã«ã®äž»é¡æãæ åœããåºãç¥ããã楜æ²ãšãªã£ãã ãœã©ãã³ã®æè©ã¯ã¢ãžã«ã³ã®äžã§å¯äžåŸè€æ£æ以å€ã®äœè©ãªã®ã ããæè©ã®ã©ããé ãæãåºãéå»ã®å¥ãæ°åãåè»ãããããªäžç芳ã«æ²èª¿ããããããåæ²ã ã 話ãæ»ããã åŸè€æ£æã®æèã®é«ããšã¯äœãã ããã¯ããã©ã³ã¡æ°ãããã§ã¢ãã¹ãããã ã¢ãžã«ã³ã¯æŽ»åãšããŠé³æ¥œã®åžæãåŸèŒ©ã®è²æãªã©ã«ç²Ÿåçã«æŽ»åããŠããã èªäž»ã¬ãŒãã«å ã§è¥æã«æ©äŒãäžããããåºãèªãããããã£ã³ã¹ãçšæãããããããã«èªåéã®ç¥å床ããã§ã¢ã«æŽ»çšããããã姿å¢ãæèã®é«ããããããã£ããããšèšãã ãããŸã§åœŒã®è©±ãèããŠããªãã»ã©ããã¯ã§è¯ã®ããç·ãªã®ã ãªãšåŸè€æ£æã«ã€ããŠèª¿ã¹ãŠã¿ãã ãããŠåãã£ãããšãããã ãã®ç·ããšãã§ããªãæ³ååãè±ã§ãããæ¥å¹Žã3/12(å), 13(æ¥) ãã·ãã£ã³æšªæµ åœç«å€§ããŒã«ã«ãŠéå¬ãšãªãã25th Anniversary Tour 2021 Special Concert âMore Than a Quarter-Centuryâã
— ASIAN KUNG-FU GENERATION Info (@AKG_information) December 22, 2021
ãªãã£ã·ã£ã«å è¡(ãã±ãããŽã)ãæ¬æ¥ã12/22(æ°Ž)18:00ããåä»éå§ã«ð
詳现ã¯ç¹èšãµã€ããããã§ãã¯ã!!https://t.co/nRJjnuu7vL#AKG25th pic.twitter.com/zrEeu8assf
æ³ååã®ããã¢ãŒãã£ã¹ã
ã³ããçŠã§ã®ã¢ãŒãã£ã¹ã掻åã®ããæ¹ã«ã€ããŠåœŒã®èããnoteã§ã¯ã©ã€ããè¡ãã¹ããã«ã€ããŠå³ã«å·Šã«ã°ã¯ã°ã¯ãšãçã ããã»ã©ã«æºãè¿·ãæ§ã綎ãããŠãããç¹ã«ãã§ã¹ã«ã€ããŠã¯ããã®ãã§ã¹ãè¡ããªãã£ãå Žåã®ã¹ã¿ãããã¡ã®é¡ãé ã«æµ®ãã³ãå¿èº«ã®ã»ãšãã©ãã°ã¯ã°ã¯ãå ããŠãããšããã é³æ¥œç£æ¥ã«ãšã£ãŠã³ããã¯å€§ææã ã£ãããããã¹ã¿ããããã®ä»ã®é¢ä¿è ã«åããŠããããŸã§æ·±ãæ³ååãåãããã¯ç°¡åãããªãã äŸãã°æ¬¡ã®åç»ãã¿ãŠã»ããã æãåãå¯æãããªãã·ã³ã°ã«ãã¶ãŒâãã©ããæ°æã¡æªãâã説æããèžèœäººãšå£®çµ¶ããã«ãSingle mother who can't love her child ãããèŠãŠããªããŠæ¯èŠªãªãã ãæäœã ããšããæããªãã®ã¯ãã£ãããªããæ¯èŠªã®ãã¡ã£ã·ãã«æ€ããåäŸã®æªæ¥ãæã以å€ã®çºæ³ãæã€ã®ãæ³ååã®äžã€ãããããªãã 人ã¯èªåãšããã®åšå²ã®åœããåããåãå ¥ããããªããèªåãåäŸæ代ã芪ã«æãããè²ã£ããããåäŸãçãŸãããããããã®ãåœããåãšãªãããããŠãã®åœããåãããªã人éã«å¯ŸããŠã¢ã¬ã«ã®ãŒåå¿ãåºãã LGBTé¢é£ã ãšåããããããããããªããèªåã¯åœããåã«ç°æ§ã奜ãã«ãªããåšããã¿ããªåœããåã«ç°æ§ã奜ãã«ãªããã ããåæ§ã奜ãã«ãªã人éãç°¡åã«ã¯ç解ã§ãããäžæåã ãšå«æªã®å¯Ÿè±¡ã«ãªãããšãå€ãã£ããïŒç§ã¯ç解ã§ãããšäž»åŒµãã人ããããããããªãããããã¯ããªãã®ç解ãé²ãã ã®ã§ã¯ãªã瀟äŒã®ç解ãé²ãã ã ãã§ãåãªãéå£å¿çãããããªããïŒ èªåã¯åäŸãã§ãããåœããåã«æãããåšãã®èŠªãã¿ããªããããŠããã ããåäŸãã§ãããæããã®ãåœããåããããã§ããªã人ã¯ã²ã©ã芪ã§äººéçã«åé¡ãããã ããã§æ³åããŠã¿ãã æãããããšã®ãªã人ã¯ã©ããã£ãŠæãã°ããã®ãã ã§ã¯åäŸãç£ãã§ã¯ãããªãã®ãã ã ãšãããããã®å®¶ã®åäŸãã¡ã¯çãŸããŠããªãæ¹ã幞ãã ã£ãã®ãã çãã®ãŒãããåé¡ãå±±ç©ã¿ã«ãªããããã»ãšãã©ã®äººã¯ãããªèªå以å€ã®ä»äººããé¢ããã®èã瀟äŒã«å¯ŸããŠæ³ååãåãããããšã¯é£ããã ããã§ãæ©ã¿ãªããçããè¡šçŸããããšããæ³ååãæã£ãã¢ãžã«ã³ã®ãããªãã³ãã玡ãé³æ¥œãªããå šå¡ã®èžã®å ã代åŒãäºãã«åãåããã£ãããäžããŠããããããããªãã -- ã¡ãã£ã¢éå¶ïŒEvening Music Records Inc.ããŒããããã¯å€©æã§ã¯ãªãããAmPmãã«æ¯ã¹ãã°
⌠ãšã³ã¿ã¡ãªãã§ã¯ã®èŠãã¿ãšã¯... çŽåŸã®çç±ã ãªããšå人çã«ã¯æãã ã¢ã€ãã«ã§ã¯ãªãã«ãããã¢ãŒãã£ã¹ãã人æ°å売ãšããŠã®åŽé¢ã¯åŒ·ãã äœåãäœãã°èªã¿æèãæã¯æå³ãæ¢ããããã¯äœãæã®ã¯ãªãšã€ãã£ããã£ã«å€§ãªãå°ãªã圱é¿ãäžããŠãããããããæå³ã§äœã£ãããããªãããšæãã°æãã»ã©æ¬¡åäœã¯æ¢åã®ãã¡ã³ã«ã¯åºãããªããªããããšãã£ãŠæ°åãåãã«è¡ãããšããã°äžéãã€ã¡ãŒãžããèåã¯äŸµé£ãç¶ããäžæ¹ãã¢ãŒãã£ã¹ãã®èªæ®ºãäžçã§ãåé¡ã«ãªã£ãŠããçç±ã¯å®¹æã«æ³åã§ããã ããã§ããã¹ã©ã ãã³ã¯ã«éããé¬Œæ» ã®åãçæã¢ãã¡ãæããŸãã€ã€è§£æ£.åŒéããã¢ãŒãã£ã¹ããªã©ã人æ°çµ¶é ã®ãªãèŠäºã«å®çµããäœåãèŠçµãã£ãåŸã«ã¯ããŸã¶ãã®è£ã§å¹é£çãªæã¡äžãè±ç«ã®æ®åãå³ãããã®ãããªå§åçãªé«ææãæ®ãããããŠæã ã¯å£ã ã«ããåãã ãç¶ããèŠããããªãã ïŒãããŸã§åæžãã§ããé·ãã£ãã...ïŒ ãããªãšã³ã¿ã¡ã®äžçãæ±ããççŸã«å¯ŸããŠãå šãæ°ããæ¹åããã¢ãããŒãããŠãã¢ãŒãã£ã¹ãããããïŒæ£ç¢ºã§ã¯ãªãã䟿å®äžã¢ãŒãã£ã¹ããšåŒã°ããŠããã ãïŒ ãAmPmïŒã¢ã ãã ïŒããšããååãèããäºãããã ãããã
⌠仮é¢ã®ã¢ãŒãã£ã¹ãAmPm èŠé¢ã被ã£ãäºäººçµã®ã¢ãŒãã£ã¹ãã§ãªã¹ããŒã®7å²ãæµ·å€ãšããä¿¡ããããç¶æ ãªãããéŠæ¥œå¥œãã«ã¯ãŸã 銎æã¿ãèããããããªããããã¥ãŒã·ã³ã°ã«ã®ãBest Part of Usãã¯Spotifyã®æ³šç®ãã£ãŒãã«ãããªãã©ã³ã¯ã€ã³ãã2017幎ã®äžçã§æãèãããæ¥æ¬äººã¢ãŒãã£ã¹ããšãªã£ããé©ãããšã«ãããŸã§ã®å瞟ã¯ããããäºåæã®ããã·ã¥ã§ã¯ãªããèªåéã®ã»ã«ããããã¥ãŒã¹ã®ã¿ã§è¡ãããŠããã ãããŠæãéèŠãªã®ã¯AmPmãã¢ãŒãã£ã¹ãã§ã¯ãªãããããŠäœè©äœæ²ãããŠããªããšããç¹ã§ããã æ··ä¹±ããã ãããšæãã®ã§ãã£ãã説æãããŠããã ããããäŒãããããäŸããšããŠæŒ«ç»ã®ç·šéè ãæãæµ®ãã¹ãŠã»ããã èªåã§æŒ«ç»ãæžãããã§ã¯ãªããããé¢çœã挫ç»ãšã¯äœãããšããç©èªã®ç¥èãšãã誰åãã«ã©ããªæŒ«ç»ã売ãããããªã©ã®ãããã¥ãŒã¹èœåãæã£ãŠãããšãããããã§ãããããªæŒ«ç»ãäžã«æ±ããããŠããã®ã§ã¯ãªããããšããã¢ã€ãã¢ãææã®ããåäœè ã«ç©èªãšããŠåœ¢ã«ããŠãããããããæèœããçµµæãã«æããŠãããã èªåã¯0âïŒã®ã¢ã€ãã¢ãšãããã¥ãŒã¹ãæäŒããåäœè ãçµµæããäœåãäžã«å£²ãåºããŠäžæ¹è¯ããšãªãã ãã®åœ¢åŒã§æèœãã挫ç»å®¶ã玹ä»ããããã®éèªã«âå°å¹Žãžã£ã³ãâãšååãã€ããã°ãâå°å¹Žãžã£ã³ãâïŒïŒãã挫ç»ãšã®åºäŒãïŒãšããå³åŒãåºæ¥äžããã ããã®é³æ¥œããŒãžã§ã³ããã£ãŠããã®ãAmPmãšæã£ãŠããã ããŠå·®ãæ¯ããªãã ããã äœè©äœæ²å®¶ã«ã¢ã€ãã¢ãæããæèœããããŒã«ã«ã玹ä»ããããã®ã¡ãã£ã¢ã«AmPmãšããååãã€ããŠæ¬äººã¯ãããã¥ãŒã¹é¢ããµããŒããããAmPmãããžã§ã¯ãèªçã®çµç·¯ã¯æ¬¡ã®éãã ãæ§ã ãªã¢ãŒãã£ã¹ãã玹ä»ãããããèªç¥ã®ç²åŸã«ã¯æåã®èªç¥ãå¿ èŠãããã§ãšããããæ²ãäœããããã1çºç®ãšããŠãããããããã«åžå Žãåæããã ...ãšãããŸã§èªãã§ãããã®ã¯ç°¡åã ãå®éã¯ãã£ãšãããã ãããšæã£ã人ãå€ãã¯ããããããã®é£ãããä¹ãè¶ãããæãããã»ã©ã«åŒ·ããã€ã³ããAmPmã«ã¯ãã£ãã 話ãè¡ã£ããæ¥ããããŠèªã¿ã¥ããã ãããããããããããããæ¬é¡ãªã®ã§ã€ããŠããŠæ¬²ããã AmPmã®1人ãYahooãã¥ãŒã¹ã®ã€ã³ã¿ãã¥ãŒã§ããèªã£ãŠããã ãã©ãã ã欲ãææ ããšãŽã殺ãããããããªãæèããŠããŸãã é³æ¥œãšãã人éã®ææ ãè¡šçŸããäžçã®äžã§ããã®ææ èªäœã«é£²ã¿èŸŒãŸãæã«ã¯ãã®æ·±æ·µããåž°ã£ãŠæ¥ãããªãè ãããäžã§ãèªã培åºããŠããã殺ããŠããã®ã§ããã âæèããŠããŸãâã£ãŠããããããã¿ããªæèããŠãã§ããããã ã©ããªæ²ã売ããã®ããªããŠã¿ããªèããŠãããç¥ãããããåªåããŠããã©ãããã§ããªãããå°ã£ãŠããã ããã«ãå®éã«ãããã§ããŠããŸãã®ããå®éã«ããã§ããºãããŠããŸãã®ããTikTokã§ã¹ã¯ããŒã«ããç»é¢ã«ããŸããŸçŸããæçš¿åæã®é³æ¥œããããã¯ããºãããšèŠæãããšãšãå®éã«ãããäœãããšã¯å šã話ãå¥ã ããããèªåã殺ããŠäœåã売ãåºãããšã«å šãšãã«ã®ãŒã䜿ããã°ãã®ç¢ºçã¯äžãããã¡ãã£ã¢ãšããŠã®å¯¿åœããã£ãšé·ããªãã YouTuberã®ã©ãã¡ãšã«ã¯ã100幎åŸã誰ããä»®é¢ã被ãã°ã©ãã¡ãšã«ã¯çãç¶ããããšæèšããŠãããAmPmãšããã¡ãã£ã¢ããã®ååãšä»®é¢ãåãç¶ãè ãããã°åççã«ã¯çãç¶ãããç¶ããæãã ãã¡ã³ã®å£°ã«å¿ãç¶ããããšãã§ããã ã¢ãŒãã£ã¹ãèåã«ããã°ãŸããããšãªãããã®é®®åºŠãæŽæ°ãç¶ããŠãããã ãªããªããæåããAmPmãšããã¢ãŒãã£ã¹ãã¯ååšããªãã®ã ããã æïŒ ç³å -- ã¡ãã£ã¢éå¶ïŒEvening Music Records Inc.
ã¢ã€ãã»ãžã»ãšã³ãã¯ãæ€åææªã®äžäœäºæãªã®ãïŒ
ãèŠã¯ããºãã°ãããã ãïŒããšæã£ãŠãã¢ãŒãã£ã¹ãããã¶ã売ããªããããã±ãã©ã³ã«ããèå¯ã
⌠ããºãã ãã§ã¯å£²ããªã ãã©ãã¯ã¯ããŒããŒã®ç¬¬ïŒã¯ãŒã«ã®äž»é¡æããBlack Roverãã§æ åœããããšã10ã¯ãŒã«ã®ãšãã«ããäžåºŠã¿ã€ã¢ããã§ãBlack Catcherããæžãäžãããããã¯ã¹ããªãŒãã³ã°ã§ã¯åäœãããåçãããŠãã äœãèšããããã£ãŠãããšã1çºã®ããºã§çµããã2çºç®3çºç®ãçµæ§ãªç¢ºçã§åœãã£ãŠãŠãããããã·ã³ãã«ã«ãããã ãã³ããŒæãæ¥æ¬2äœã ãïŒã£ãŠèãããŠãåããããã æ¥æ¬ã§2çªç®ã«é«ãå±±ãã2çªç®ã«åºãæ¹ãç¥ãããã ãã®ã¢ãŒãã£ã¹ãã®2çªç®ã«äººæ°ã®æ²åããïŒã£ãŠèãããŠããã»ãšãã©ã®äººã¯åãããŸããããããããã®ã§ãã ããããã¿ã€ãã«ååããŸãã ã売ããã«ã¯ãšããããããºãã°ãããã£ãŠã®ã¯æ£ãããã ãã©ã1çºããºã£ãŠãç°¡åã«ã¯è»éã«ä¹ããªãã®ãã¢ãŒãã£ã¹ãã£ãŠããä»äºã®é£ãããšããã§ãåœç¶ã ã¢ãŒãã£ã¹ãã«éããã¯ãªãšã€ã¿ãŒãäžçªèŠããã®ã£ãŠ1çºãããããåŸã«é³Žããé£ã°ãã«ãªãææãããªã£ãŠã®ã¯æããŸããçŸã«ããºã£ãã®ã«ããæ¶ããå±€ã¯åããæ³åãããããã£ãšååãã ãããªäžã§ãã£ã¡ãã»ã«ã³ãããºãæç«ããŠããã²ãã³ãšãããã±ãã©ã³ã«ã£ãŠãã£ã±ããããã ãªãšæ¹ããŠæããŸããã ãããã°ããã±ãã©ã³ã«ã®æ°æ²ãåæäžæãã¢ãã¿ããã«ããã£ãŠãŸãã ãã£ã±ä¿ºã¯ãã©ãŒãã奜ãã§ãããŠããŒãããã±ãã©ã³ã«ã®è£å£°ããã£ã¡ã奜ãã ãµãã®ïŒããããèšã£ãŠãªããªïŒãããããšãã©ãã£ãŠãããŒãã® âã©â ãè¯ãã ããåããããã©ãã£ã¡ã奜ããããã ãã§ãããã§èããŠãã ããã"ã©" ã ãã§ãããã§ã ä»¥äž åèæ å ± â» ããã±ãã©ã³ã«å ¬åŒTwitterïŒ https://twitter.com/VickeBlanka â» ããã±ãã©ã³ã«ãåæäžæãYouTubeåç»ïŒ https://youtu.be/wH5QbrEs8mY â» ããã±ãã©ã³ã«ãBlack RoverãYouTubeåç»ïŒ https://youtu.be/8RSfSxkN0ek
ãSKY-HIããã人çãè³ããŠæãææŠãšã¯…ïŒ
ã¢ãŒãã£ã¹ãã§ãããããã¥ãŒãµãŒ
ãããªã«äœè¶³ãã®ãããå±¥ãããªããŠãã®å€§è°·ç¿å¹³ãããããç¥ãããã ãããããããã¥ãŒã¹æ¥ãšçŸåœ¹ã®ã¢ãŒãã£ã¹ã掻åã䞊è¡ããŠãã®ããããã ããªãã ãTHE FIRST TAKEã§ãäœæ§ããæã£ãŠãŸããŠã2021/10/22ã®æç¹ã§400äžåçã«é«è©äŸ¡8.9äžãããã¯ãã£ããã¡ãããšäººæ°ã®äººã®æ°åã§ãã è£æ¹ãåŸæãªã®ããšæã£ãããã£ããé³æ¥œåã匷ããã»ã«ã³ããã£ãªã¢ãšããããè²ããªè·æ¥ãåæ䞊è¡ã§ããªããã©ã¬ã«ãã£ãªã¢ã®é³æ¥œçã«ããã1äŸãšããŠå¿ããå°æ¬ããŸãã ...ãšããŸããããŸã§åœŒã®ããããé·ã 䞊ã¹ãŸããããå人çã«äžçªããããšæã£ãŠãããšãè¿°ã¹ãŸãã 䜿åœæã§ãã â» SKY-HI à ããªã - äœæ§ feat. ãŒãã®ããã£ãã®ãŒããã¿ / THE FIRST TAKEéããªããŠã売ããäžç
é³æ¥œçãèŠãŠãŠæ¥æ¬ãäžçã«å£ã£ãŠãã£ãŠã®ã¯å ±éèªèã ãšæããŸããã ã£ãŠäžçã§ãããã ãã 圌ã¯ããã§æ¢ãŸããèªè ¹ã§1ååºããŠãŸã§æ°ããã¢ãŒãã£ã¹ããçã¿åºããŠäžçãšæŠãããšããŠãã 1åã§ããïŒ çŽ çŽã«æããŸããïŒ ãªãã§ãããŸã§ãããã ã£ãŠã 圌ã¯ã¢ãŒãã£ã¹ããšããŠãã§ã«æåããŠããã§ãè¥ãæèœãåãããŠãã®ãèŠãŠããŠåããã«ã¯ããããªãã£ãã俺ãªãçŽ éããŸãã ãã³ã¬ããã¯ãã³ãã®äž»äººå ¬ã挫ç»å®¶ãšããŠé£ã¹ãŠããããã®3æ¡ä»¶ãæããŠãŸãã 1. ãã¬ãŒã 2. åªå 3. é ãã¬ãŒããã»ã©èªä¿¡ãæã£ãŠé²ãã åªåããã ãããŠéã ããããã¯æšæž¬ã§ãã SKY-HIã¯ãããããã®3ã€ç®ã®æ¡ä»¶ âéâ ã®èŠçŽ ããªããããšããŠãã ã¢ãŒãã£ã¹ããšããŠæåããã«ã¯éãå¿ èŠã£ãŠã®ã¯å šå¡ããã£ãŠããã©ããã ãããçŽåŸãããªãããããªãããšãããã§èª°ãããããªãããããªããã俺ãããããšã ã€ã³ã¿ãã¥ãŒã§ããªã1åãïŒãã£ãŠèãã㊠ãèªåã®äººçãè³ããŠãããããããšçããŠãŸããã ãããŒäººãããããã§ããã æãã€ããŠãããããæ®éã çŽ çŽã«å¿æŽããããšæããŸããã æ¬æ°ã§æ代ãå€ããããšããŠããã ãªãšã äžè¬äººã®èªåãäœãè²¢ç®ããããšæã£ãããSKY-HIã®äºåæããããã¥ãŒããåã®ãBE:FIRSTãã®æŽ»åã®ããã«ã¯ã©ãŠããã¡ã³ãã£ã³ã°ãããŠãããã§ãäžå©ã«ãªããããšããæ¹ã¯æ¯éèŠãæ¹ããããšæããŸãã -- ã¡ãã£ã¢éå¶ïŒEvening Music Records Inc.ãDa-iCEãã®æã¯ãªãæããããªãã®ã…ïŒ
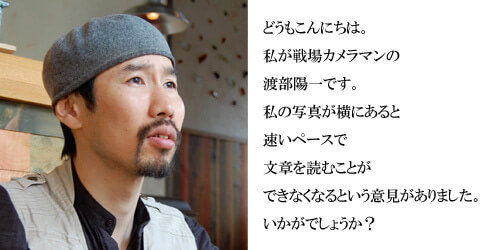 確ãã«ãªãã
ãªãããäœãã«è² ãããããªæ°ãããŠç
®ãåããªãææ
ã«ãªãã
人éã¯ç¹å®ã®æ
å ±ãè³å
ã§èªåçã«ãªã³ã¯ãããçãç©ããããæç« ãé»èªãããšãã«ããã®é³ããªã³ã¯ããæ
å ±ã«åºã¥ããŠè³å
åçããããäºäžäºã®æååèŠãããšãããããã®ãªãºã ã§èªããããã¿ãããªãã€ã
ã§ã¯ãã¿ãªããã次ã®æç« ããã©ããªé³ãåçãããŸããïŒ
ããé¢ããªãã£ãŠæ±ºããããã
ããå®ãããã£ãŠèšã£ãã®ãã
ã¯ãããããªã£ããªããã£ãŠããŒãŒããããããããŒããŒãŒãŒ
ãŸããããããããããŒãã£ã£ãŠãŒãããããã‵ïžã®ãŒããŒãŒ
...以å€ã®é³ãè³å
åçããã人ã«ã¯ãŸã£ããäŒãããªãæç« ããããš1,200æåãããç¶ãã®ã§ããŸãMVãèŠãŠãã ããã
5人çµãã³ã¹ããŒã«ã«Da-iCEã®ãCITRUSãã§ãã
ãšããããèŠãŠããŠãã ããã
â» CITRUS / YouTubeåç»ïŒ
確ãã«ãªãã
ãªãããäœãã«è² ãããããªæ°ãããŠç
®ãåããªãææ
ã«ãªãã
人éã¯ç¹å®ã®æ
å ±ãè³å
ã§èªåçã«ãªã³ã¯ãããçãç©ããããæç« ãé»èªãããšãã«ããã®é³ããªã³ã¯ããæ
å ±ã«åºã¥ããŠè³å
åçããããäºäžäºã®æååèŠãããšãããããã®ãªãºã ã§èªããããã¿ãããªãã€ã
ã§ã¯ãã¿ãªããã次ã®æç« ããã©ããªé³ãåçãããŸããïŒ
ããé¢ããªãã£ãŠæ±ºããããã
ããå®ãããã£ãŠèšã£ãã®ãã
ã¯ãããããªã£ããªããã£ãŠããŒãŒããããããããŒããŒãŒãŒ
ãŸããããããããããŒãã£ã£ãŠãŒãããããã‵ïžã®ãŒããŒãŒ
...以å€ã®é³ãè³å
åçããã人ã«ã¯ãŸã£ããäŒãããªãæç« ããããš1,200æåãããç¶ãã®ã§ããŸãMVãèŠãŠãã ããã
5人çµãã³ã¹ããŒã«ã«Da-iCEã®ãCITRUSãã§ãã
ãšããããèŠãŠããŠãã ããã
â» CITRUS / YouTubeåç»ïŒ












